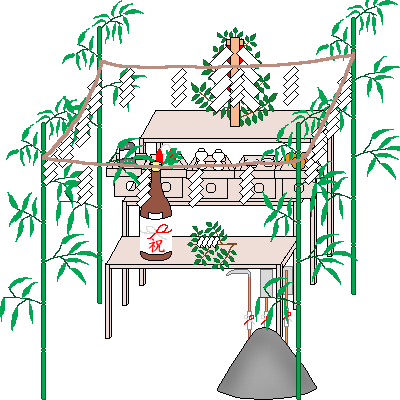■神社が行うまつりには、例大祭、祈年祭、新嘗祭、歳旦祭、元始祭、紀元祭など様々なものがある。ここでは、一般的なまつりの儀式(祭式)がどのようなものかを理解するために、地鎮祭を取り上げたい。
■現在の形態の地鎮祭が行われるようになったのは江戸末期からと言われているから、地鎮祭自体はそれほど伝統のあるものではない。しかし、地鎮祭には「まつり」の儀式が実にコンパクトに集約されている。なお、地鎮祭に関する記述は日本書紀にも見られ、どのように執り行われていたかは不明だが、このまつり自体は古くから行われているものである。
■現在の地鎮祭は、一般的に、以下のような流れで進められる。
(1) 神籬(ひもろぎ) はじめに、土地の中央に4本の青竹を差し、そこに注連縄(しめなわ)を渡して祭場とする。そこに、神籬(ひもろぎ)と呼ばれる神の依り代(よりしろ)を設置する。神籬は、木の台(八脚台)の中央に、紙垂(しで)を垂らした榊(さかき)を置いたものである。神籬は土地の神を招く場所となる。神籬の前には、酒・水・米・塩・野菜・魚などをお供えする。
(2) 修祓(しゅばつ) 参列者および祭場を祓い清める。
(3)降神(こうしん) 土地の神を神籬(ひもろぎ)にお迎えする儀式を行う。神職が「おおー」と声を発して降臨が告げられる。
(4)献饌(けんせん) 祭壇の酒と水のふたを取り、お供えもの(神饌)を土地の神に食べていただく儀式を行う。
(5)祝詞奏上(のりとそうじょう) 神職が祝詞を奏上する。祝詞の内容は、土地の神にお供えものをし拝礼をしますので、建物の基礎が揺らぐことがないこと、棟や梁に狂いが生じないこと、工事関係者が無事に工事を進められることなどを祈願する。
(6) 四方祓(しほうはらい) 土地の四隅をお祓いし清める。
(7) 地鎮(じちん) 施主が忌鎌(いみがま)で盛り砂の草を刈るしぐさをし、設計会社が忌鍬(いみくわ)を3度突き立てる所作を行い、最後に、施工会社が忌鋤(いみすき)を3度突き立てる所作をする。
(8) 玉串奉奠(たまぐしほうてん) 神前に玉串を奉り拝礼する。
(9) 撒饌(てっせん) 神職が神饌(しんせん)を下げる儀式を行う。
(10) 昇神(しょうしん) 招いた神を送る儀式を行い神事は終了する。
■現在の地鎮祭は、土地の神様をお呼びし、捧げものをし、祝詞を述べ、祈願をし、玉串を奉り、神様にお帰りいただくという流れで進められる。あたかも、土地の神様を客人のごとく接待するのが神道のまつりなのである。
☛神道とは何か
祭る(祀る)ということ